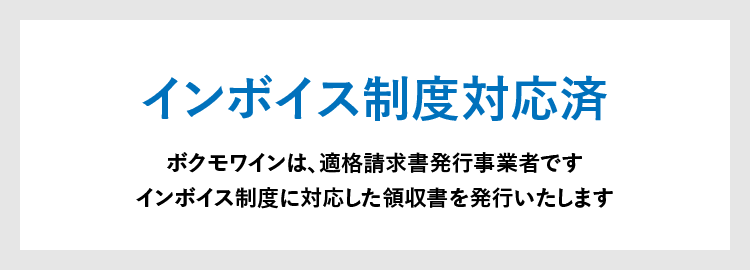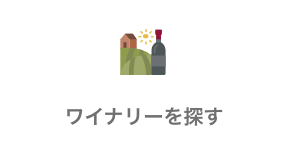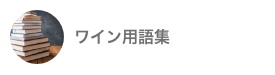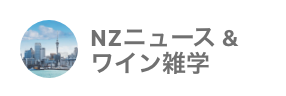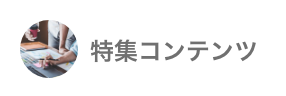言語化できない
IWASUNaoki先週、横浜に行ってきました。RADWIMPSのライブを見るためです。 去年、彼らは北米、ヨーロッパ、日本を含むアジア、オーストラリアをまわるというツアーをやりました。どの都市も現地のファンで会場をいっぱいにし、大いに沸かせたそうです。 もはや世界のラッド。新海監督3部作で完全に彼らの音楽は海を越えたのです。 世界ツアーを成功させて、今年は日本でどっしり腰を据えてアルバムでもつくるのかな、と思っていました。が、まったく違いました。 今年もまた世界ツアーをやっているのです。 まだ行っていなかった地球の裏側の南米へ、そしていつも熱狂的だという何回目かのアジアへ。 彼らもスタッフの皆さんもとんでもないバイタリティーです。 そして改めて「ジャパニメーションといっしょに世界に出る」という発明の凄まじさを感じます。こんな地球規模のツアーをやっている日本のバンドはたぶん他にいないです。 今回、日本公演は5つのみ。名古屋はナシなので、横浜へ。 通算十数回彼らのライブを見ていますが、彼らの地元横浜でライブを見るのはおそらく4回目です。 今はもうないライブハウスの横浜BLITZで2回。初のアリーナ公演となった横浜アリーナのライブも見させていただきました。あのとき、いよいよ凄いバンドになるぞ、と思ったなあ。 そして、僕にとって久々の横浜が先週でした。 まずは中華街で春巻きを食べ(昔の彼らのツアータイトルにちなんで)、DeNAファンたちの大歓声がこだまする横浜スタジアムをかすめて、みなとみらいへと歩きました。 繁華街のど真ん中にできたぴあアリーナMM、良いところでした。音が実に素晴らしい。 開演から終演まで、文字通りあっという間の時間でした。懐かしい曲の数々が、腹にどーん、どーんと響きました。 音に集中すればするほど、頭の中が忙しくなる。過去と今を行ったり来たり。数分間が数年に感じるほど、内なる長い旅をしていました。 気付けば目尻から熱いものがこぼれていました。 終わったあと、心になにか大きなものが湧き上がりました。 この感情をどう表現したら良いんだろう。 じわっと暖かい。嬉しい。ありがたい。 その中に少し、焦る気持ちも混じっている。胸騒ぎも。寂しさも。 でもなんか違う。そういう言葉の羅列じゃ、しっくりこない。 香りや味の言語化はソムリエの必須能力で、練習して少しはできるようになったけど、自らの内側からくるこういう複雑なものを言葉にする能力は、僕にはてんでないようです。 いやむしろ、この感情に名前をつけると、なにか限定されてしまう気がしてもったいない気がする。 もわっとした暖かい塊のまま、引き出しにしまいたい。 ありがとう、ボクモがんばります。 秋に予定されている野田洋次郎ソロアルバムも楽しみにしています。 というより、野田洋次郎、RADWIMPSと同じ時代に生きていることを、これからも人生の楽しみとします。 そうそう、旧友オチケンと会場でばったり。これもラッドのおかげです。 思えばオチケンといっしょに番組をやっているときにラッドを応援しはじめたんだった。あれは2004年のことだった。もう20年経つんだな。...